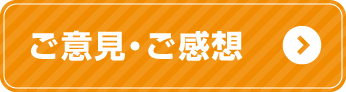在宅ケアケース事例Home care case example

国際医療福祉大学大学院
医療福祉学研究科
教授 石山 麗子氏
大切なのは、ケース個々の価値を見出すこと。
本人支援の立場から丁寧なケアマネジメントを。
ケアマネジャーの力量が問われるのは困難ケースとは限りません。重度ではなく、良好な家族関係、経済的不安のない利用者でも、作成したケアプランの中にケアマネジャーの深い配慮や経験知が垣間見えることが多々あります。本ケースがその一つ。何の変哲もないケースのようですが、ケアマネジャーはそこに固有の価値を見出し丁寧に対応しています。尊重すべきその価値とは、90代まで生きてこられた、そのご夫婦ならではの「家」の意味と、妻の「役割」。それらをイマジネーション豊かに意識化し、ご本人のプライド、生きがい、在宅生活への意欲と関連づけて見事にケアプランに反映しています。
今回の事例

わかばケアセンター立石
主任介護専門員・管理者
遠藤 貴美子氏
支援経過
階段から落ちて大腿骨骨折
Aさんを担当して1年になります。年齢は90歳で、94歳になるご主人と2人、一軒家で暮らしています。ご本人は要介護1、ご主人は今も自立状態を維持。90代のご夫婦にしてはともに認知症の兆候が見受けられず、とてもお元気なご夫婦といえます。
前任のケアマネジャーが退職し、引き継ぐ形で私が担当することになりました。ご夫婦で鉄工所を経営されてきたというAさんは、「自分でできることは自分でしよう」「介護度は低いままで結構、むしろ要支援を目指したい」という、ポジティブ思考の持ち主。ケガをする前は海外旅行を楽しみ、後期高齢者の仲間入りをしてからも週3回プールに通うなど、とても活発な人だったと聞いています。
そんなAさんが、右足大腿骨転子部(足の付け根部分)骨折という大ケガをしたのは今から2年前のこと。高齢者が転倒した際に最も骨折しやすい箇所です。夜中にトイレに行こうとして階段を踏み外し、2階から下まで転落してしまいました。事故直後はリハビリ専門病院に入院し、3ヵ月間に及ぶ厳しいリハビリ訓練を経て退院しました。以来、独力による歩行が難しくなりました。家事や買い物は、基本的に夫か二人の息子(週2回来訪)の手を借りて。外出は誰かが付き添うか、シルバーカーを利用しています。
2階の物干しに洗濯物を干したい
伝い歩きでトイレまで行けるし、入浴も夫が在宅時は可能というAさん。現在利用している介護サービスは、週1回の訪問リハビリのみ。右股関節付近の痛みをやわらげるのと、股関節の可動域を広げることが目的です。Aさんには具体的なリハビリ目標があります。それは、ケガする前のように洗濯物を2階の物干しに干せるようになること。もとは工場だった広々とした台所には、ベストポジションバーをジャングルジムのように組み合わせ、それを手すりがわりに伝い歩くことで転倒予防に努めています。夫や息子たちからの厳命もあり、行動範囲を1階に絞られてしまったと伺いました。2階に上がらなければ階段を利用することもなく、転落リスクもないとの理由からです。
しかしAさんにはこれが不満のタネ。そこで、2階に上がって自分一人で洗濯物を干せるようになることを目標に掲げ、訪問リハの訓練プログラムを組んでもらっています。ただ、骨折から回復する際のリハビリ専門病院での施療が相当こたえたらしく、「痛いのにむりやりリハビリをさせられた。あんな痛い思いは二度とゴメンだ」が口癖になっています。訪問リハのPTには、階段昇降を中心とした運動、立ち上がって両手離しで洗濯物を干す動き、バランス能力の向上などのトレーニングプログラムを組んでもらい機能回復に努めています。
生き抜いてきた時代が違う
年を経るごとに利用者さんの高齢化に拍車がかかり、Aさん夫婦のように90代も決して珍しくない時代になりました。最近時折感じるのが、利用者さんとケアマネジャーの私たちとの世代間ギャップです。戦中・戦後をたくましく生き抜いてきたバリバリの昭和世代と私たちでは、生き方や価値観自体が違うという思いが強くなってきました。
例えばAさんの場合、味噌汁を自分でつくることに強いこだわりを持っています。立ち仕事はつらいでしょうに、私などはインスタントの味噌汁にお湯を注げばいいのにと考えてしまいますが、Aさんにとっては論外のこと。生活の随所にそうした世代感覚の違いが生まれていたとしたら問題かもしれません。
でも、当面は大きな問題はないようです。ご主人が在宅中は家事も買い物も手伝ってくれるし、お風呂も家で入れます(浴槽またぎはできない)。シャワーなら自分一人でも可。また週に2回ほど、長男と次男が様子を見に来ては通院と買い物を支援してくれるので、日々の生活の不自由は感じていません。現在は工場を改装した自宅(持ち家)に暮らしており、経済的にもゆとりがあります。2人きりの暮らしにいずれ限界が来たら、そのときは施設入所という選択肢を息子さんたちは考えているようです。
事例概要
利用者/A氏(90歳・女性)
要介護1
(令和7年10月現在)
障害高齢者の日常生活自立度/B1
既往症/右大腿骨転子部骨折 高血圧
食事/椅子座位にて自力摂取。
夫と息子が購入した惣菜、菓子パン、配食弁当摂取。
排泄/屋内伝い歩きをしながらトイレに行く。
念のためパッド使用(月1回程度失敗)
入浴/夫がリビングにいるときに入る(介助なし)。
浴槽またぎができず、シャワーなら1人で可。
ADL/屋内は伝い歩き、屋外はシルバーカー。
見守りで移動可能レベル。
IADL/右股関節付近に痛みがあり。家事は基本的に夫が支援、自分でも
行う。立ち仕事はつらいが、1日1回必ず味噌汁を作る。
家族/夫(94歳)と二人暮らし。長男と次男が交代で週2回訪問し、買い物と通院を支援。
利用中の介護サービス/訪問リハビリ(週1)
社会交流/40年以上在住。近所づきあいは活発。
※本人およびご家族の許可を得て掲載しています。(一部修正あり)
今回のポイント
関係良好なご家族との意見対立を踏まえながら、
利用者さんが生きてきた時代を熟慮しつつ
本人支援のケアを注意深く実現した好事例です。
生きてきた時代が違う
利用者は90歳代、私たちよりもずっと長く生きてこられた方です。しかも現代のようにジェンダーの認識がなく、女性は家の中を守り、家事が上手であることが美徳とされた時代を生きてきました。転落・骨折したからといって、これまでの生活を大きく変えることには無理があります。これまでの生き方を続けていくことが生活の支えとなり、自分の自信となるからです。60年間この家で生活してきました。工場も営んできましたが、家事は女性の仕事という考え方がしっかり体に染みついていて、それ自体が生き甲斐・矜持・意欲となっています。ケアマネジャーはそこをしっかり踏まえたうえで、ご本人支援の立場からケアプランの作成に取り組みました。
意見の対立とリスクを感じながら
ご家族からすれば、もう危ないのだからじっとしていてくれという気持ちでしょう。もう2階には上がらず1階で暮らしてほしい。つまり、ご本人との間には意見の対立があります。ご本人の希望通り、転落する前のことができるようなリハビリテーションにもっていくとしたら、そこにはケアマネジャーの責任が伴います。洗濯物を干すときは両手を上にあげるので、重心は後ろにかかります。わざわざ転倒リスクのある行為をリハビリテーションに盛り込んでいくことは、ご家族の「転落・転倒をしないように暮らしてほしい」という願いに反します。再び転倒事故が起きた場合、ケアマネジャーは家族から責めを負うリスクを否定できない。「あなたがこんな計画を立てたから」といわれかねません
ゆるやかな関係の築き方が素晴らしい
こうした対立の構図がある中、ケアマネジャーは実に巧みに両者の関係を調整し、結果的にはこれこそが本人の価値を実行していくという方向で精緻な対応を実現しています。これこそがケアマネジメントの“意向の調整”機能だと思います。同時に、通所介護や訪問リハなど、それを実現していく“サービス調整”機能を発揮しています。単に生活目標を実現する手段としてのサービスではありません。
ケアマネジャーは“意向の調整”の手段として、敢えて別居の長男を本人の日常に、息子さんの負担も考慮しながら関与してもらいました。例えば、買い物や通院同行の継続を通じて、本人の思い、身体の状態、日常の努力などを感じられる機会をつくったのです。このケースは、家族関係は良好ですが、意向には対立があります。家族間の意向をどう調整するか。本人の立場に立ち、家族の理解を深める関わりを(柔らかく)行っていっているようにみえます。このようなケアマネジャーの営みはケアプランには記載されない部分ですが、確かにケアマネジャーとしての専門性をもって意図的に行われています。だからといってご本人やご家族からみて強引さはなく、むしろ温かみを感じる柔らかな関わり(調整)をしてもらっていると映っているのではないでしょうか。
ケアマネジャーの力量が地域の高齢者の生活の質を上げる
いかにも困難ケースという場合、ケアマネジャーは専門家と相談するなど非常に丁寧にケアマネジメントを展開します。それに比べると、90歳代の利用者さんで、特段大きな問題もない、ともすれば平凡な事例かもしれません。しかし、どんな事例にも固有の価値があるものです。そこを見逃すことなく、注意深く丁寧かつ、意図的に対応した事例かと思います。
近年、後期高齢者が要介護者の大半を占めるようになりました。加齢に伴う心身機能の低下はあっても、いくつになっても、できるかぎり、これまでしてきたその人の生活を継続する可能性を簡単に手放さない、丁寧に考えてくれるケアマネジャーが担当してくれるならこんなに心強く幸せなことはありません。こういうケアマネジャーが地域に増えると、その地域の高齢者の安心度や生活の質はずいぶん違ってくると思います。