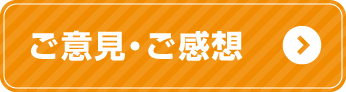ズームアップひとZoom up Person

合同会社イノチテラス
浅原 聡子氏
1968 年静岡市生まれ。小児専門病院に約20 年間看護師として勤務。多くの出会いと別れを経験し、人生における喪失・グリーフというテーマに出会う。2013 年3 月、グリーフカウンセラーとして独立し、相談業務や講演活動に従事。2016年度~2018年度、静岡大学非常勤講師。2023年1月、高齢者が人生最期の時間を安心して暮らせる“看取りの家”イノチテラスを開設した。
看護も介護も、
どれだけ頑張っても人の命の責任はとれません。
責任がとれるのは自分の仕事においてだけです。
経済産業省(中国経済産業局)がYouTubeに発信した動画サイトに、まだ歴史の浅い静岡の介護事業所が紹介された。珍しいことだ。動画は資本力も経営実績も皆無に等しい一人の看護師が介護事業を立ちあげたことに焦点を当てている。それよりも、「イノチテラス」という施設名に象徴される浅原代表の高齢者介護のスタンスや人となりが気になり、取材を申し込んだ。正直で飾らない物言いの裏に、利用者への深い想いがあふれていた。

数十年ぶりに高齢者介護の現場を経験
ひどすぎるケアの現状にショックを受けて
静岡市駿河区の高齢者向けマンション。2年前。そのワンフロアを借り上げ開設されたのが、看護小規模多機能型居宅介護、訪問看護、住宅型有料老人ホーム(13床)の3機能を併せ持つ高齢者介護施設、その名も「イノチテラス」だ。施設名には“出会った人とお互いがいのちを照らし合う”という願いが込められている。
皆さんとてもいいイメージを描いて取材に来てくださいますが、私、皆さんが思うよりエゴイスティックだと思います。正直なところ、人の役に立ちたいというより世界がこうあって欲しいという気持ちが強いのだと思います。グリーフケアを個人で開業していたとき、生活のために老人ホームや病院で夜勤のバイトをしていたのですが、数十年ぶりに老年期の看護に身を置いて介護現場のあまりのずさんさというか、利用者さんが大事にされていない現場やケアの実情に大きなショックを受けました。そこも原点のひとつです。そのころには医療ケアが必要な人、ご家族のケアだけでは大変な人、終末期を迎えて不安な人も、安心して過ごせる“看取りの家”の青写真が出来上がっていました。
とはいえ、資本力も経営実績も何もないただの看護師です。どうやったら介護事業を一から起こせるのか…。起業したいとか社長になりたいとか、一度も考えたことのない人間です。親友の助言もあって、2016年に静岡県中小企業家同友会に入会しました。それから5年間、いろんな勉強会に参加して事業経営のイロハを学びました。

何をしちゃダメかではなく、
何をしたいかを聞いて育てたい
すごいのはここからの実行力だ。浅原さんは思い描く10年先の事業像を内閣府が推奨する「経営デザインシート」にまとめ、金融機関の門をたたいた。結果、4つの金融機関から無担保融資を受けることに成功したのだった。(経済産業省発信のYouTube動画あり)
まだ世の中にないものをやろうとすると今の既存のモデルには乗れない現実があります。自分で創造してやらない限りそれはかなわないし、できたとしても時間がかかりすぎてしまう。グリーフカウンセラーを始めたときもそうだったけど⋯私よりもやさしくて、リーダーとして人をまとめるのが上手な人はいっぱいいます。でもね、そういう人は優しさゆえか行動まで至らない。だから、私ぐらいが日々もがきながらやるのがちょうどいいのかなって。今では、ある意味では天命なのかなと思っています。
採用面接などで、これからウチで働きたいというスタッフに会いますね。みんな転職組で、看護師や介護士としていくつもの現場を渡り歩いてきた人ばかりですが、いつも感じるのは「プレッシャーに押しつぶされそうになりながら仕事をしてきたんだな」ということ。みんな「頑張れば何とかなる」といった責任を負わされた現場で育てられてきた。あれをしちゃいけない、これをしちゃダメとか、教えられることはネガティブなことばかり。不思議なことに、本当は何をしたいかか、利用者さんとどういう時間を共有したいか、人権を守るってどういうことか、といった本質的な話はしてきていない。
精神論だけでは介護現場は決して良くならず、せっかくの人材がただ疲弊するばかりです。看護師や介護士は人の命に責任を持ってといわれるけれど、そもそも他人の命の責任を持てるわけないですね、責任がとれるとしたら自分の仕事においてだけだと、私は考えています。

日勤は7時間、入りは19時半から
看護師は24時間常駐しています
イノチテラスは看護多機能、訪問看護が共存し、訪問時も宿泊時も顔なじみの職員が対応してくれる。高齢者にとって大変心強いことだが、イノチテラスの最大の特徴は、施設内に看護職員を24時間配置し、胃ろうなどの医療処置が必要な人や重度の認知症に対応して最期までの穏やかな時間と心地よいケアを実現していくこと。
いつでも看護師がいる。これは利用者さんやご家族はもちろんのこと、職員にとってもいいことでした。なかでも介護士はとても安心して働けるみたいです。昨今の高齢者施設は看取りまで求められています。でも実際は人手不足の中、看護師がいない施設でも看取っているという現実があります。とても頑張っていらっしゃるけれど、介護士の負担は少なくないと思います。どこかで「心配だな」とか、「自分の夜勤のときに当たらないでほしい」とか考えてしまうものだから。
利用者さんだけでなく、職員にもやさしい施設でありたいと考えています。例えば日勤は7時間勤務で、正社員でも週35時間。入りは19時半ですから介護業界では遅い方です。なぜなら、夕食の準備を済ませてから安心して出勤してもらいたいから。残業もなくしています。離職率は低い方ではありません。というより、今どき、どんな業種でも転職は当たり前。離職率が低く、長く勤務している人が多ければ良い組織、といった考え方はもうやめませんか?それよりどれだけ理念と個々の良さを共有して仕事ができるかなのではないでしょうか。

介護は無形資産
仕事を創る、創造性を楽しんでほしい
開業から2年1か月が経過した。メディアにもしばしば登場するし、介護業界における浅原さんの認知度も日増しに高まっている。10年ビジョンに描いた「看取りの家」は、今どのあたりまで形になりつつあるのだろうか。
思った以上の施設になってきている、それが正直な感想です。ゴールはまだまだ先だけど、私のビジョンにスタッフのビジョンが重なって、相乗効果で思った以上のことが日々起きています。
昔からよく言われたように、介護職には3K(きつい、きたない、危険)という感覚がまだあります。それなのに給料は安いと。そうじゃなくて、ものすごく創造性のある仕事だということに気づいてほしいのです。要するに介護って無形資産なんです。目には見えにくいけれど確実にある想い、それが豊かな何かにつながっていくのを実感することができれば働くことが楽しくなる。私は結構信じていますよ、職員の中にそういうものが確実に芽生えていることを。
連絡先
合同会社イノチテラス
〒422-8054
静岡市駿河区南安倍3丁目12番1号ガーデニアガーデン南安倍2階